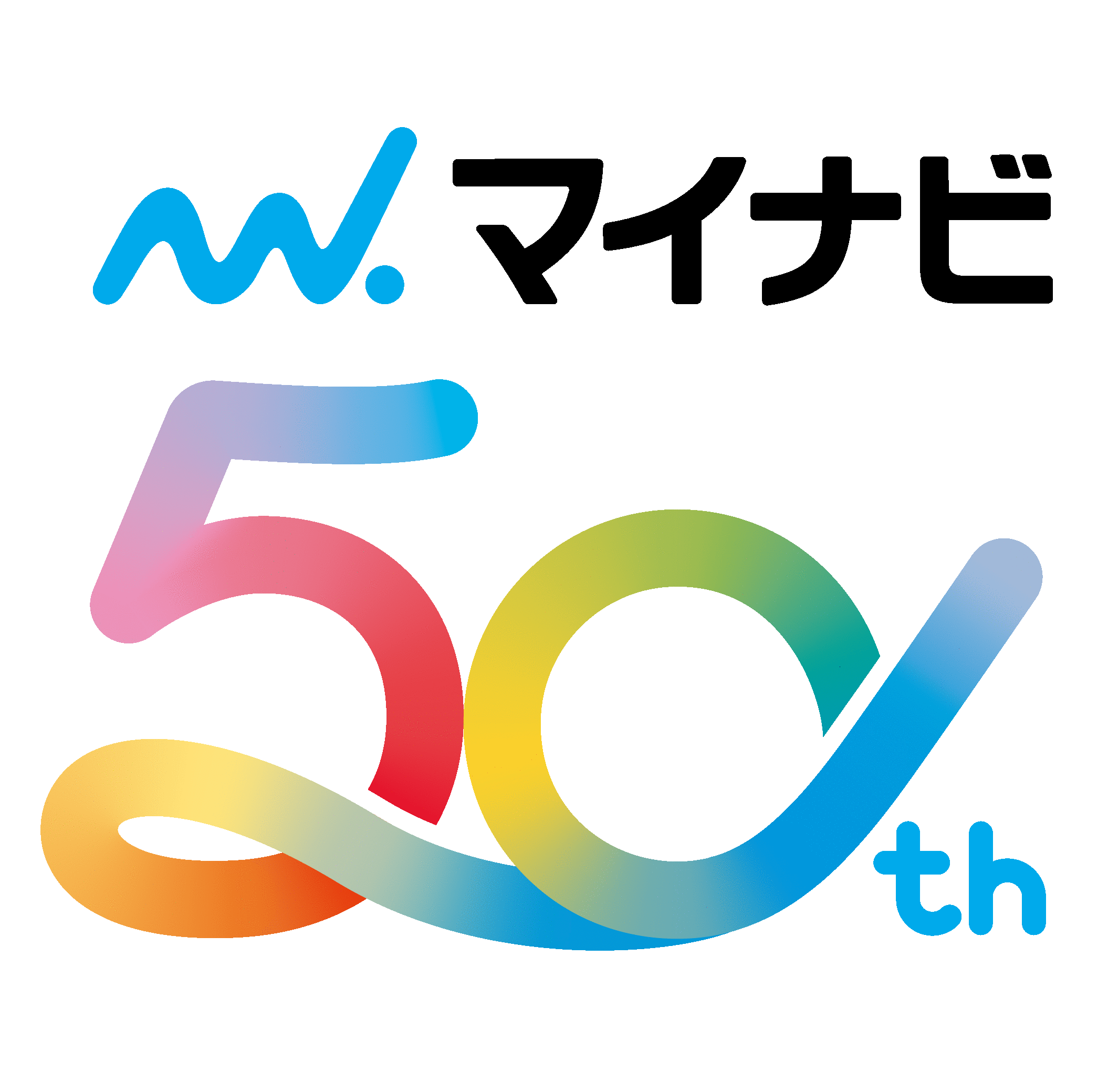2013年6月に閣議決定された「日本再興戦略」では、
- 女性の活躍促進や仕事と子育て等の両立支援に取り組む企業に対するインセンティブ付与等
- 女性のライフステージに対応した活躍支援
- 男女が共に仕事と子育て等を両立できる環境の整備
を3本柱として特に力を入れていくことを、日本政府は発表しました。*1
この政策は、女性の出産・子育て等による離職の減少や、管理職に占める女性の割合の増加に向けた施策を盛り込んだものです。
しかし実際のところ、女性が仕事と家庭生活を両立させるのは、並大抵のことではありません。
現実には結婚や出産を機に、仕事をやめて家庭に入ってしまう人も少なくないのです。
そこで今回は「女性が結婚した後でも働きやすい企業」をランキング形式でご紹介していきます。
結婚しても長く働き続けることを考えている方は、ぜひ参考にしてください。
女性を取り巻く社会情勢
近年では、少子高齢化が深刻な社会問題となっています。
下図1を参照すると、昭和45年から平成26年にかけての女性を取り巻く状況は、大きく変化をしていきました。
ここでは、女性を取り巻く社会情勢について、詳しく解説をしていきます。
平成26年における平均第1子出産年齢は30.6歳
下図1は、内閣府 男女共同参画局が平成27年度にまとめた「女性を取り巻く状況の変化」を表した表です。
参照すると、女性の平均寿命は74.66年から86.83年へと大きく伸び、総人口に占める65歳以上人口の割合である高齢化率も、7.1%(昭和45年)から26.7%(平成27年)と大幅に上昇。
また、女性の平均初婚年齢は24.2歳(昭和45年)から29.4歳(平成27年)と5歳以上も上昇し、平均第1子出生年齢は25.6歳(昭和45年)から30.6歳(平成27年)へと上がりました。
初婚年齢と比例する形で、第1子出生年齢も上昇しているといえるでしょう。
なお、女性の大学進学率は6.5%(昭和45年)から47.6%(平成27年)へと大きく上昇し、25歳から29歳までの女性の労働力率も45.5%(昭和45年)から80.3%(平成27年)と、こちらも大幅に増えました。
相関関係や因果関係の程度は不明ですが、女性が学歴を身につけ、社会で活躍するにつれて、晩婚化や晩産化の傾向が増加している形です。

I-特-2図 女性を取り巻く状況の変化
女性は子育てがひと段落すると、就業する人が増えていく
下図2は「育児を行っている人の割合・育児者に占める有業者の割合」を表したグラフです。
平成24年の「未就学児の育児を行っている人の割合」のデータですが、女性は10.3%、男性は7.6%となっており、育児者の割合は男性より女性の割合の方が多いといえます。
また、育児者における有業者の割合は、男性が98.5%であるのに対し、女性は52.3%しかおりません。
年齢階級別に見ると、男性はどの年齢階級でも同じような割合ですが、女性は25~29歳で47.7%、40~44歳で56.7%と、年齢が上がるにつれて有業率が増えていくのが特徴です。
このようなことから、子育てに手がかからなくなっていくと、仕事を始める女性が増えていくのがわかります。

I-特-5図 育児を行っている人の割合・育児者に占める有業者の割合
女性が結婚しても働きやすい企業ランキング
このような状況では、仕事と子育てを両立し、安心して働くことができる環境に多くの女性が魅力を感じるのは当然のことと言えるでしょう。
逆に言うと、魅力ある人材を採用するため、企業はもっと積極的に女性の活躍を支援していくことが必須である時代になったとも言えそうです。
そのためここでは、そのようなことに積極的に取り組む、結婚後も女性が働きやすい企業ランキングをご紹介していきます。
データの参照元として、就活四季報 女子版の「女性の既婚率が高い企業」を用いました。
一般的に女性が結婚している割合が高い企業は、結婚後も働き続けやすい傾向があるようです。
既婚率だけでなく、勤続年数や女性社員の離職率も見ていきましょう。
【女性の既婚率が高い企業 TOP10】※既婚率、勤続年数、離職率は女性のみのデータ
| 順位 | 企業名 | 業種 | 既婚率 | 勤続年数 | 一般社員 離職率 |
| 1位 | サンデンホールディングス | 自動車部品 | 90.6% | 14.0年 | 10.0% |
| 2位 | 中部電力 | 電力・ガス | 79.7% | 19.3年 | 2.3% |
| 3位 | ミツトヨ | 機械 | 76.9% | 17.0年 | 2.3% |
| 4位 | 石油資源開発 | 石油 | 76.8% | 15.0年 | 3.7% |
| 5位 | ジヤトコ | 自動車部品 | 74.3% | 20.0年 | NA |
| 6位 | 医学書院 | 出版 | 71.4% | 16.6年 | 0% |
| 7位 | 花王 | 化粧品・トイレタリー | 70.4% | 13.2年 | 3.2% |
| 8位 | 東京電力ホールディングス | 電力・ガス | 66.6% | 22.3年 | 2.1% |
| 9位 | JSR | 化学 | 66.2% | 14.2年 | 2.4% |
| 10位 | 日立物流 | 運輸・倉庫 | 66.1% | 16.5年 | 4.2% |
P32 P98 P362 P375 P407 P428 P482 P592 P600 P607 P688 を参考に筆者作成
既婚率が高い企業は女性の勤続年数が長い
既婚率が高い企業1位は、自動車エアコン用コンプレッサーで世界2位の「サンデンホールディングス」(90.6%)となりました。
但し、同社は2020年6月30日、私的整理の一種である事業再生ADR(裁判以外の紛争解決)制度の利用を申請し受理されており*2、今後の採用計画に影響があると思われます。
2位は「中部電力」の79.7%、3位は「ミツトヨ」の76.9%と続いています。
全体的に見ると既婚率が高い企業は、女性の勤続年数が13年以上と長い傾向があります。
「東京電力ホールディングス」は22.3年、「ジヤトコ」は20.0年と、女性社員が20年以上もの長い期間にわたって働いているのです。
厚生労働省が調査した「令和元年賃金構造基本統計調査」によると、女性の平均勤続年数は9.8年となっています。*3
比較すると、既婚率が高い企業で働いている女性の平均勤続年数は、平均より長めといえるでしょう。
離職率も低い傾向がある
社員の平均勤続年数が長い企業は、一般的に働きやすい職場が多いようです。
そのため、平均勤続年数が長い企業は離職率が低い傾向があります。
今回ランクインした女性の既婚率が高い企業は、ADRという特別な事情があるサンデンホールディングスを除くと、離職率が3%前後の企業が多くなっています。
全体的に女性の離職率が低いといえるでしょう。
医学書院においては離職率が0%となっており、女性が長く働ける会社であることが読み取れます。
女性の就労と家庭の現状
ここでは、女性の就労と家庭の現状について、詳しく見ていきましょう。
妊娠・出産前後に退職した理由は「家事・育児に専念するため」が最も多い
下図4は、内閣府がまとめた「妊娠・出産前後に退職した理由」を表したグラフです。
参照すると、1番目と2番目は「家事・育児に専念するため自発的にやめた」39.0%
「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた」26.1%となっています。
出産・育児を機に労働市場から退出する女性が多くなっています。
現実問題として、子どもを育てながら仕事もバリバリこなしていくというのは、なかなか難しいといえるでしょう。
日本では、男性より女性の方が、家事や育児を主に担わなくてはならないという風潮があり、女性に負担がかかりやすいのが問題となっています。

共働き世帯数は年々、増加傾向
昭和55年においては「専業主婦がいる世帯」は1,114万件、「共働き世帯」が614万件となっており、「専業主婦がいる世帯」が圧倒的に多い状況でした。
しかし、平成に近づくにつれて「共稼ぎ世帯」が少しずつ増え始め、平成4年頃には、ついに「共働き世帯」が「専業主婦がいる世帯」を上回ったのです。
その後も「共働き世帯」は右肩上がりに増えていき、平成22年には「共稼ぎ世帯」が1,012万世帯、「専業主婦がいる世帯」は797万世帯と、大きな開きを見せています。
もはや「女性の活躍」は見栄えの良い目標ではなく、企業が存続していく上での「条件」であると言っても良い時代になったと言えるでしょう。

まとめ
今回は「女性が結婚した後でも働きやすい企業」について、現代の日本における女性を取り巻く社会情勢を考察しながら、ランキング形式でご紹介をしていきました。
「共働き世帯」は年々増加しており、結婚して子育てをしながら、仕事と両立している女性もたくさん存在しています。
「女性は結婚したら退職して家庭に専念する」といった時代は過ぎ、近年では、既婚女性が働きやすい環境を整えている企業が、優良企業と言えるのではないでしょうか。
これから就職や転職を考えている女性の立場でいうと、
- 既婚女性の割合が高い
- 女性の勤続年数が長い
- 女性の離職率が低い
という3つのポイントを重視して、会社を選ぶとよいでしょう。
【無料】人材紹介事業者向けセミナーのアーカイブ配信
現在、人材紹介事業を行っている方はもちろん、
人材紹介事業の起業を検討中の方向けの動画もご用意しております。
求職者集客から求人開拓まで、幅広いテーマを揃えていますので、お気軽にご視聴ください!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
視聴料 :無料
視聴手順:
①下記ボタンをクリック
②気になるセミナー動画を選ぶ
③リンク先にて、動画視聴お申込みフォームにご登録
④アーカイブ配信視聴用URLをメールにてご送付
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
【エビデンス】
*1(参考)内閣府 男女共同参画局「男女共同参画白書(概要版) 平成26年版」
1.成長戦略の中核としての女性の活躍促進
*2(参考)日本経済新聞「<東証>サンデンHDが売り気配 新型コロナで業績悪化、私的整理へ」
*3(参考)厚生労働省 令和元年賃金構造基本統計調査「(2) 性別にみた賃金」
【参考資料】
1. 就職四季報女子版2022年版 P32-33
2. 就職四季報女子版2022年版「サンデンホールディングス」P362

【著者】矢口 ミカ
フリーランスの転職・不動産ライター。複数のメディアで執筆中です。宅建の資格を活かし、家族が所有する投資用不動産の入居者管理もしています。住まいに関する資格である整理収納アドバイザー1級、福祉住環境コーディネーター2級も取得済みです。趣味は整理収納と時短料理。