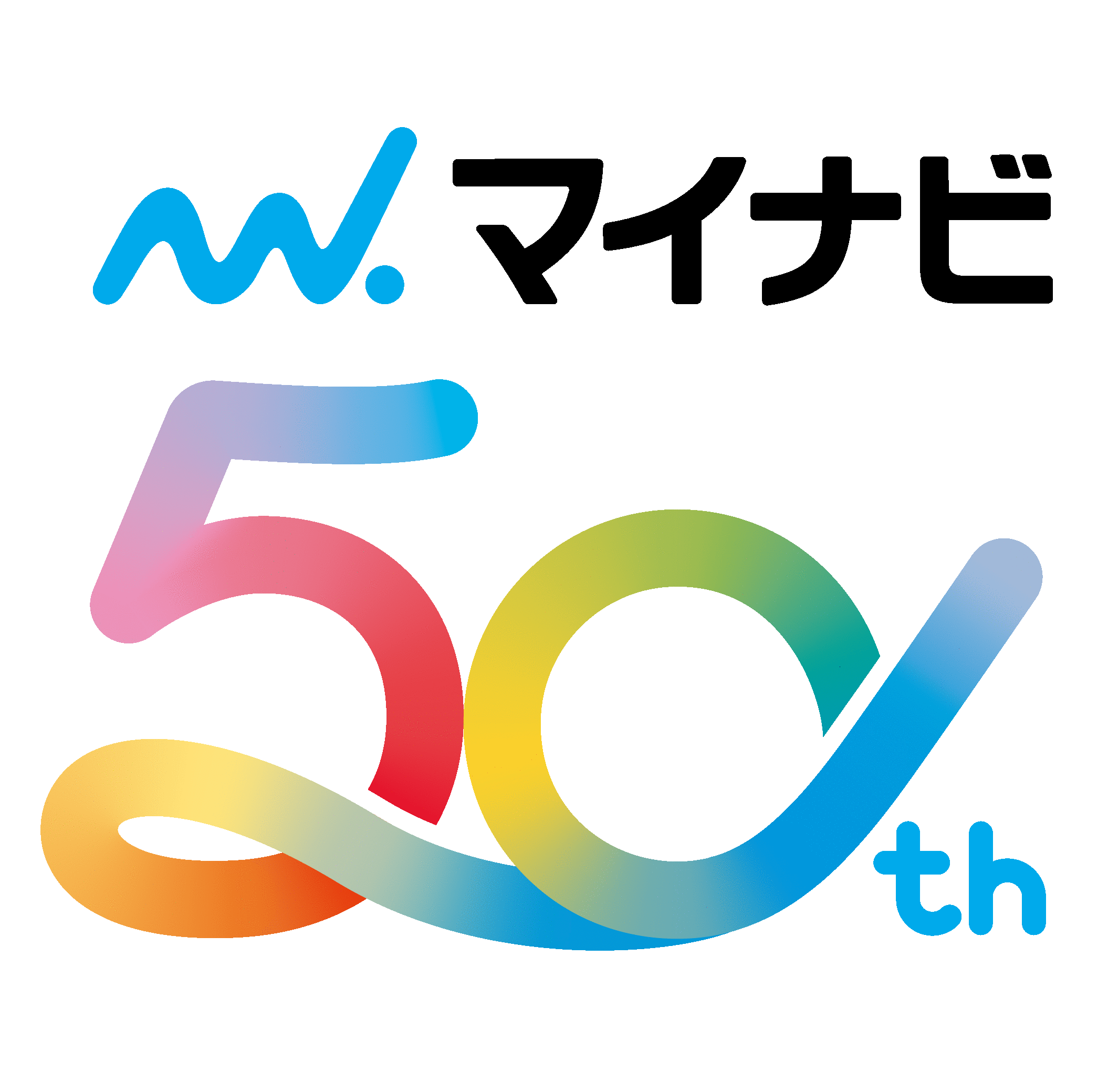転職が内定した会社と雇用契約を締結する際には、会社から労働条件通知書が交付されるのが一般的です。会社との間で認識の齟齬をなくすためにも、労働条件通知書の内容はきちんと確認する必要があります。
しかし、労働条件通知書は入社当日に交付されることもあり、その場合はじっくり労働条件を確認する時間が取れません。そのため会社に対して、事前に労働条件通知書を交付するよう求めることが望ましいでしょう。
今回は労働条件通知書について、記載事項やチェックポイント、もらえるタイミング、入社前に詳しい労働条件を確認したい場合の対処法などをまとめました。
労働条件通知書とは
労働条件通知書とは、会社が雇用契約(労働契約)を締結する従業員に対して、労働条件を明示するために交付する書面です。
会社には、従業員の入社時に労働条件を書面で明示することが義務付けられているため(労働基準法15条)、労働条件通知書を交付するのが一般的となっています。
労働条件通知書に記載すべき事項
会社が従業員に対して、明示することを義務付けられている事項は、以下のとおりです(労働基準法15条1項前段、労働基準法施行規則5条1項)。明示された労働条件が事実と相違する場合、従業員は直ちに雇用契約を解除できます(労働基準法15条2項)。
<明示すべき労働条件>
(1)絶対的明示事項
必ず明示しなければならない事項です。
・労働契約の期間
・(有期雇用の場合)労働契約を更新する場合の基準
・就業場所
・従事すべき業務
・始業および終業の時刻
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間
・休日
・休暇
・(交代制を採用する場合)就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期
・昇給
・退職(解雇の事由を含む)
(2)相対的明示事項
会社が定めている場合には、必ず明示しなければならない事項です(定めていない場合には、明示する必要はありません)。
・退職手当
・臨時に支払われる賃金
・賞与
・精勤手当
・勤続手当
・奨励加給または能率手当
・最低賃金額
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
・安全および衛生に関する事項
・職業訓練
・災害補償および業務外の傷病扶助
・表彰および制裁
・休職
上記のうち書面による明示が義務付けられているのは、絶対的明示事項のうち、昇給に関する事項を除く事項です(労働基準法15条1項後段、労働基準法施行規則5条3項。下記参照)。したがって労働条件通知書には、以下の事項について漏れなく記載することが求められます。
<労働条件通知書により明示すべき労働条件>
・労働契約の期間
・(有期雇用の場合)労働契約を更新する場合の基準
・就業場所
・従事すべき業務
・始業および終業の時刻
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間
・休日
・休暇
・(交代制を採用する場合)就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期
・退職(解雇の事由を含む)
特にチェックすべき労働条件通知書のポイント
会社と従業員の間で、特に認識の齟齬が生じやすい以下の労働条件については、労働条件通知書の記載を必ず確認しておきましょう。
(1)転勤の有無・範囲
労働条件通知書において転勤があり得る旨が明示された場合、その範囲内での転勤命令には、原則として従わなければなりません。転勤の有無・範囲については、入社前に必ずご確認ください。
(2)時間外労働の上限時間
時間外労働の上限時間は、労使間で締結される「36協定」により決まっています。
原則として「月45時間・年360時間」の範囲内とする必要がありますが(労働基準法36条4項)、36協定の特別条項によってそれを超える時間外労働が認められているケースもあるので注意が必要です(同条5項)。
(3)残業代の取扱い
会社によっては、残業代について以下のような運用がなされている場合があります。
・裁量労働制のため、残業代の計算方法が通常と異なる
・固定残業代制のため、毎月一定の時間(固定残業時間)までは残業代が発生しない
・管理監督者のため、残業代が一切発生しない
など
会社によるこれらの運用は、労働基準法のルールに従って行われなければなりません。もし会社の運用に疑問がある場合には、労働基準監督署などへ事前にご相談ください。
(4)退職金・賞与の支給基準
退職金や賞与は大きな金額になるケースも多いため、入社前に支給要件を必ず確認しておきましょう(会社によっては、支給がない場合もあります)。
特に、今後もさらなる転職によるキャリアアップを考えている方は、転職予定者の退職金や賞与を減額または不支給とする旨が定められている場合には要注意です。
労働条件通知書は必ず交付されるのか?
入社時の従業員に対する労働条件の明示は会社の義務とされているものの、「労働条件通知書」という名称の書面が必ず交付されるとは限りません。
労働基準法で義務付けられているのは、労働条件の「書面」による明示であって、労働条件通知書以外の書面による明示も認められます。
たとえば雇用契約書を締結して、従業員側が原本または写しを保管する場合、契約書の中に明示すべき労働条件がすべて記載されていれば、労働条件通知書の交付は不要です。
また、従業員が希望した場合には、書面ではなくファクシミリ・電子メール等による労働条件の明示も認められます(労働基準法施行規則5条4項)。
労働条件通知書を受け取っていない場合は、会社からファクシミリや電子メール等を受け取っていないかについても念のためご確認ください。
労働条件通知書はいつもらえるのか?
会社が従業員に対して労働条件を明示しなければならないのは、労働契約の締結時とされています(労働基準法15条1項)。
入社前に転職内定が出る場合には、内定時点で雇用契約が成立すると解されています(最高裁昭和54年7月20日判決、大日本印刷事件)。
したがって、会社は求職者との間で内定の合意をする際に、労働条件通知書の交付などによって労働条件を明示しなければなりません。
これに対して、内定を経ずに即日契約・入社となる場合には、労働条件通知書は入社時に交付すればよいことになります。
内定前・入社前に詳しい労働条件を確認するには?
労働基準法のルールに従うと、求職者は内定を受諾する段階、あるいは入社する段階まで、労働条件通知書の交付を受けられない可能性があります。
しかし、それでは会社からのオファーを受けるべきかどうか、十分に吟味する時間を確保できないでしょう。
雇用契約書にサインするかどうかは、求職者の自由です。そのため、会社に対して労働条件通知書の事前交付を求め、雇用契約書の締結は後日とすることをお勧めいたします。
特に転職活動が必ずしも順調でなかった場合には、
「会社の怒りを買ってオファーを取り下げられたら困る」
といった心理から、労働条件通知書の事前交付を求めることを躊躇してしまうかもしれません。
しかし、内定前・入社前の段階で労働条件をきちんと確認しなければ、入社後に後悔する可能性が高まってしまいます。
労働基準法を遵守し、従業員を大事にする会社であれば、労働条件通知書の事前交付にも応じてくれるでしょう。早く転職したいと焦る気持ちを抑えて、転職後の労働条件をじっくり確認・検討してください。
【無料】人材紹介事業者向けセミナーのアーカイブ配信
現在、人材紹介事業を行っている方はもちろん、
人材紹介事業の起業を検討中の方向けの動画もご用意しております。
求職者集客から求人開拓まで、幅広いテーマを揃えていますので、お気軽にご視聴ください!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
視聴料 :無料
視聴手順:
①下記ボタンをクリック
②気になるセミナー動画を選ぶ
③リンク先にて、動画視聴お申込みフォームにご登録
④アーカイブ配信視聴用URLをメールにてご送付
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
【著者】阿部 由羅
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
HP:https://abeyura.com/
Twitter:https://twitter.com/abeyuralaw